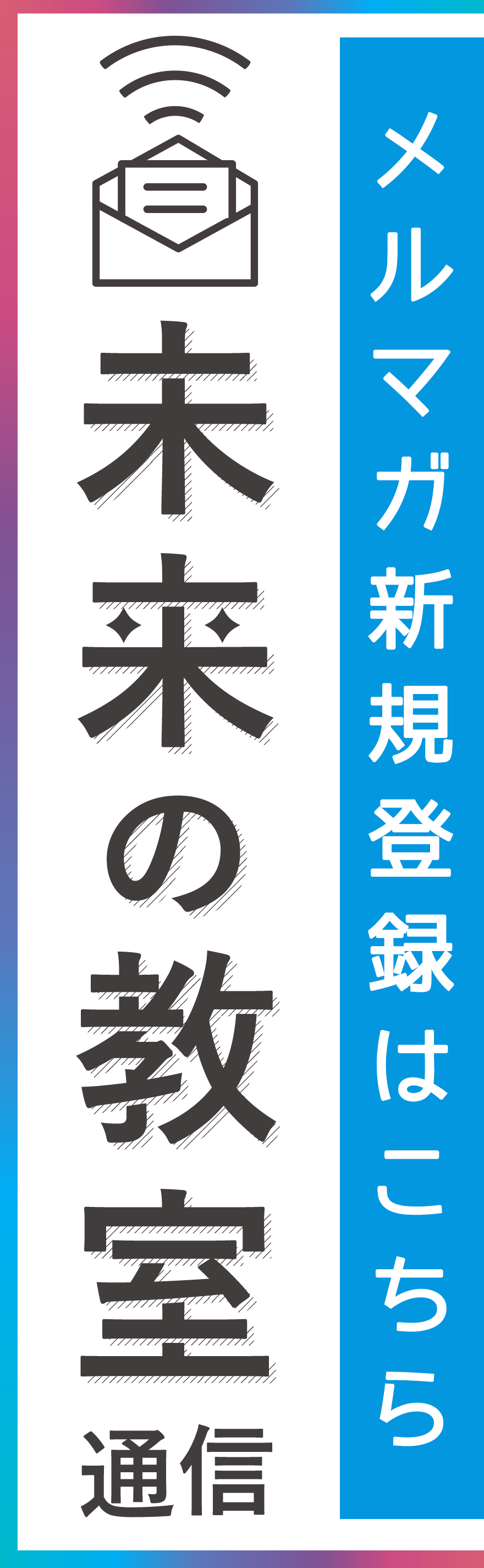教員とZ会サポーターによる、AI教材を用いた、学校での数学の教科指導の最適化
実証事業 報告書
本事業について
目的
AIと人の指導を掛け合わせた 「修得のスピードアップ」と「理解の深化」の両立を実現を目指します。
概要

本実証では、実証校の教員とZ会が派遣する「サポーター」が連携して、通常の数学の授業にAI技術を活かした教材「atama+」を活用しています。
atama+では一人ひとりの生徒の学習ログを分析し、個別最適化された問題が出題されます。同時に、教員やサポーターが持っているiPadの「コーチ向けアプリ」には、「同じ問題を何度も解いています」「解説の動画を飛ばしているかもしれません」「そろそろ目標を達成しそうです」といった通知が多数飛んできます。
こうした最適な問題の出題と、それに対応する情報をリアルタイムに出してくれるのがAIの役割だとすれば、通知された情報を参考に生徒の表情や様子も見ながら、励ましたり、配布されている紙のノートを見て解き方を確認したり、という部分が「人」の役割です。こうした「人」の指導と「AI」の活用を両立させることで、従来よりも「より深く」「より確実に」数学を理解してもらうとともに、「全ての生徒が数学を楽しめる学校」を目指しています。

本事業を開始するまで、学校では週4コマの、一般的な一斉指導型の数学授業を行っていました。一方、2学期からはatama+を採用した授業を週4コマ中3コマで展開。9月は、かなりハイペースでAI技術による指導を推進しました。中には、小学校での「算数」の知識に一部課題が残ったままという生徒もいましたが、その「弱点」をAIによる診断で特定し、補強することで「どこが分からないのか分からない」という課題を克服できた生徒も出てきました。
一方で10月からは、atama+を用いた授業を週2コマにして、空いた1コマでPBL(Project Based Learning:プロジェクト型学習)を行っています。ここは、プログラミング教育サービスを展開するLife is Tech! 様が、数学で修得した内容を活かしながら、「ゲーム」を題材にしたワクワクする学びを提供しています。

本実証を展開するにあたり、重要なのは先生と一緒に授業内で生徒の皆さんをサポートしている「サポーター」です。サポーターは、年齢も性別もバラバラで多様なバックグラウンドを持つ方々を公募し、厳密な選考を経て選出し、研修と模擬授業を経て教室に入ってもらっています。写真は、学校の先生とサポーター、Z会スタッフが混ざって最後の確認である「模擬授業」を行っている様子です。

実際の授業では、サポーターの動きや声のかけ方、教員との連携など、様々な課題が出てきます。それらを関係者の間で共有し、「どういうタイミングで声をかけると良いのか」
「つい数学が苦手な子に目がいきがちだが、クラス全体がより良くなるためにどう動くか」など、日々改善を進めています。また、atama+には宿題を配信する機能もありますので、その効果的な使い方も打合せを経て詰めていきます。
本実証では事前と事後には数学のアセスメントによる効果測定も行いますので、AIと人による指導のアウトプットを最大化し、「週2コマのAI学習でも十分な効果が出ている」ことをきちんと示せるよう、学校と関係者が一体となって試行錯誤をしているのです。
atama+の最大の特長は「さかのぼり学習」と呼ばれる、関連する前の単元にさかのぼって理解を確認し、弱点を早期に発見できる機能があります。この機能によりきちんと前段となる内容を理解したうえで、上位の内容の積み上げを確かなものにしていくという「完全習得学習」と呼ばれるアプローチをとっています。
そのため、単に「公式を使って問題が解ける」だけではなく、前段となる知識など考え方を含めた「理解の深化」が期待できます。
成果
実証環境
実証校ではiPadの一人1台環境が導入されており、学校が構築したWiFi通信環境を活用して生徒の皆さんは日々、学んでいます。
この中に、AI教材「atama+」をインストールしていただき、正課の数学の授業時間内でatama+を用いた個別最適化学習を行っています。
※atama+は塾向けの製品であり、今回の実証では特例として事前に研修を受けたサポーターを派遣することで学校での利用を可能にしています。
実証校以外の学校への展開については現時点で未定です。
実証校の先生と生徒も登壇し、今回の実証について自分の言葉で語ってくれました。
「Edvation×Summit2019」での中間報告会
2019年11月4-5日に東京都千代田区で開催された教育の大規模イベント「Edvation×Summit 2019」。このイベント期間中に開催された「未来の教室」実証事業の
中間報告会に、武蔵野大学中学校の先生と生徒が登壇してくれました。
生徒のみなさんが、自分の言葉で実証事業について語ってくれています。ぜひ動画をご覧ください。
https://www.facebook.com/watch/?v=522244558507197

お問い合わせ先
「未来の教室」実証事務局
https://www.learning-innovation.go.jp/faq/
サービス情報サイト
https://www.atama.plus/
ダウンロードコンテンツ
ー
サービス事業者サイト
https://www.atama.plus/
| 実証事例名 | 教員とZ会サポーターによる、AI教材を用いた、学校での数学の教科指導の最適化 |
|---|---|
| 受託事業者名 | 株式会社Z会 |
| 実証パートナー名 | atama plus株式会社 |
| 実証年度 | |
| 事業カテゴリー種別 | |
| 実証地域 | 東京都西東京市 |
| 実証校 | 武蔵野大学中学校・高等学校 |
| 対象 | |
| 対象者 | 2019年度の実証校 中学校入学者 |
| 対象学年 | 中学校第一学年 138名 |
●このサービスをご覧の方はこんなサービスもご覧になられています。
-
地域を超えた学びのサード・プレイス
-
教師のわくわくを中心にしたPBL型業務改善で...
教師のわくわくを中心にしたPBL型業務改善によって、「授業と学校組織の変革につながる」「教師の新しい専門性は向上する」という2テーマをまと...
-
「化学分野におけるデジタル人材」を育成す...
化学分野を担う産官学関係者が本事業を通じて、化学の専門性に加え「データ科学」を活用し、情報とのインターフェースを担う人材を育成するし、...
-
ゲームをテーマにした中高生の可能性を引き...
ゲームをテーマに中高生の可能性を引き出す探究型STEAM教育を実現する
-
震災復興からのSDGs@釜石を題材にした人材...
・現実の社会課題を題材とした、実践的能力開発プログラムの構築。 ・主体性、課題設定・発見力等を身につけた「課題解決・変革型人材」の育成。
-
智慧の風〜観察と感覚で、違いを捉え、未来...
興味関心に無自覚な児童生徒が自らの興味関心が動くまで学びから逃げずにいられる環境をミュージアムにて提供し、興味関心が芽生えたときに最短...
-
『ハッケンLENS 〜リアルテックベンチャーの...
①STEAMライブラリをアントレプレナーシップ教育の文脈で活用できるか検証、②起業ゴールではない起業家”精神”教育に資する教材開発、③反転学習と...
-
学校独自の財源づくりのための資金調達・運...