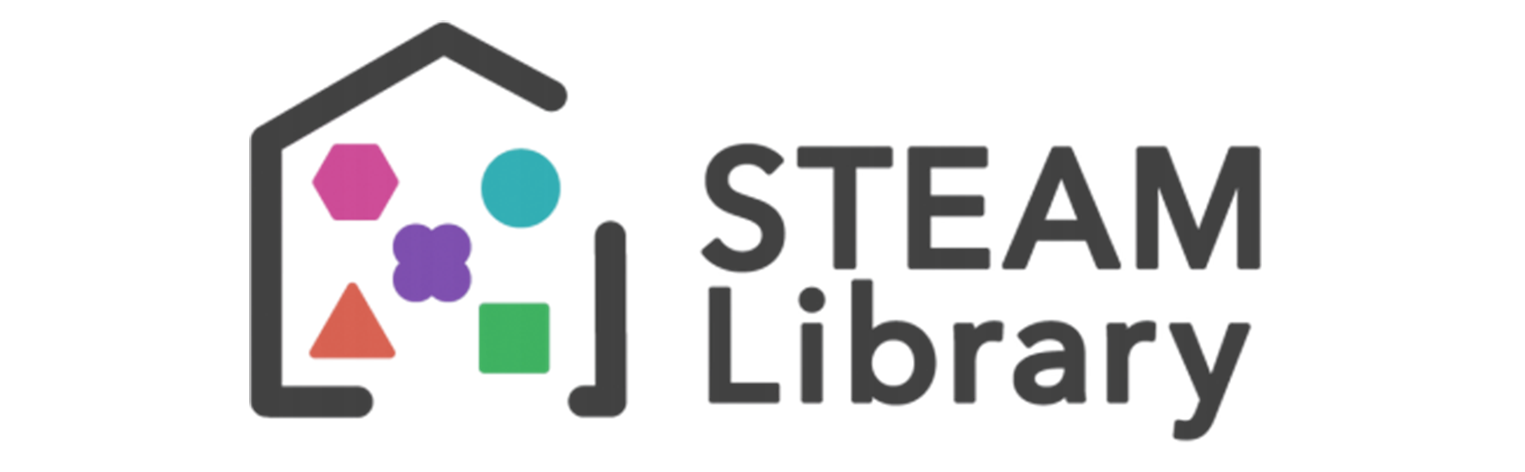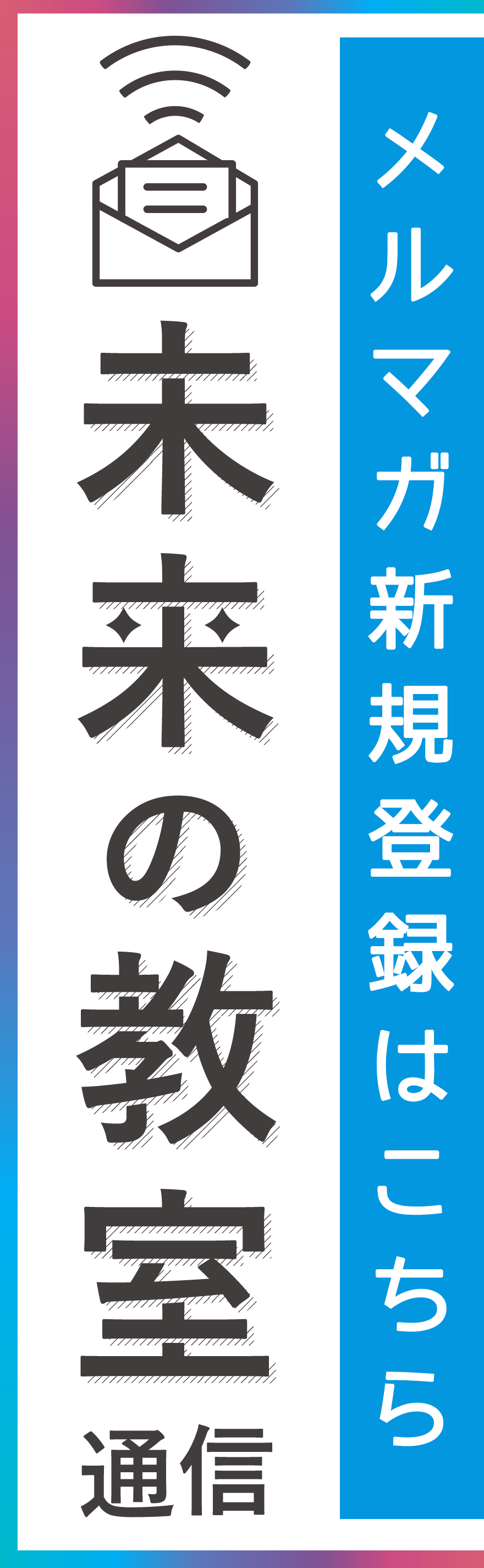STEAM化ごんぎつね普及計画
実証事業 報告書
本事業について
目的
STEAM化ごんぎつねは、情報活用能力、学びのSTEAM化、仮説演繹を用いた探究学習の3本柱で構成されます。
本件で、授業でのSTEAM化を深化させ学校種を超えた利活用、教委への認知拡大を目指しました。
概要
関西大学初等部小4の実践

関西大学初等部4年生の「STEAM化ごんぎつね」実践について、担当教員と児童のインタビューと、授業の様子を記録しました。
初めての「STEAM化」に戸惑いながらも、児童も教員もワクワクして、児童が主体的に学んだ様子が伺えます。
関西大学初等部小5の実践

関西大学初等部5年生の「STEAM化ごんぎつね」実践について、担当教員と児童のインタビューと、授業の様子を記録しました。
また、小学5年生社会科の「水産業」と「ごんぎつね」に出てくる「いわし」をテーマに連携した授業の様子も記録しています。
関西大学初等部小6・小3の実践

関西大学初等部6年生で、「STEAM化ごんぎつね」に着想を得て、「授業のSTEAM化」をした実践と、担当教員と児童へのインタビューを記録しました。
また、3年生では、PBLをする際に「STEAM化する視点」を重視した担当教員のインタビューを記録しました。
関西大学初年次教育の実践

大学での初年次教育における「クリティカルリーディング」の教材として、「STEAM化ごんぎつね」を利用した講義の様子と、担当教員のインタビューを記録しています。
関西大学初等部主催の研修

関西大学初等部主催の「STEAM化ごんぎつね」の研修(前半部:公開ウェビナー、後半部:宮津市教育委員会研修)の一部を記録しました。
STEAM化することでのワクワクする授業を生み出す秘訣について、教員視点から説明しています。
成果
関西大学初等部小4の実践

関西大学初等部4年生で、児童の興味関心に基づく「STEAM化」や「探究的な学び」を導入した「ごんぎつね」の授業を実践した。児童はフィクションとノンフィクションを区別し、物語を読み進めながらクリティカルシンキングをし、図書館資料や映像を参考に、疑問を調べ、意見交換など対話的な学びができた。教員主導の読解だけでなく、背景理解に基づく主体的な学びが実現でき、児童と教員がワクワクする学びができた。
関西大学初等部小5の実践

関西大学初等部5年生で、児童の興味関心に基づく「STEAM化」や「探究的な学び」を導入した「ごんぎつね」の授業を実践した。児童は「問いを自ら作る」ことに腐心しながら深い学びができた。また「ごんぎつね」と社会科での「水産業」が連携した授業では、児童から次々に「問い」が生まれた。「STEAM化」した授業を実践する前段階として、小学校低学年から「原経験」を積み重ねる重要性について述べている。
関西大学初等部小6・小3の実践

関西大学初等部6年生で、STEAM化ごんぎつねに着想を得て応用した「STEAM化浦島太郎」の授業を実践した。児童は「多角的にみる視点」に気付きながら深い学びができた。また3年生で実践した総合学習の授業では、「STEAM化」の概念を児童が捉え、ワクワクからの「没頭」が生まれた。「授業のSTEAM化」を実践する上で、教員と児童が共に授業を構築する指導観の変化が重要であることを発見した。
関西大学初年次教育の実践

関西大学の1年生の学生に対し「初年次教育」の中で、アカデミックスキルを教授するが、その際に、「STEAM化ごんぎつね」を利活用した。文章を作成する際、初中等教育での感想文と大学での論理的な文章作成では大きな違いがあり、その理解を体感する意味で、学生が慣れ親しんだ「ごんぎつね」をクリティカルリーディングすることで、学生の中で文章作成の違いの気づきが生まれ、ワクワクしながら取り組め、成果を得た。
関西大学初等部主催の研修

関西大学初等部では、2022年度に、京都府教育委員会研修、宮津市教育委員会研修、関西大学初等部主催セミナーを実施した。「STEAM教育とはなにか」、「STEAMライブラリーを利用した授業の構築」「STEAM化ごんぎつねの実践にあたって」と、主に初等教育関係者に研修をした。最初は文学作品のSTEAM化に戸惑う参加者もいたが、研修を通じて、自身もSTEAMライブラリーを活用して挑戦したいと参加者に意欲が湧いた。
実証環境
児童数約360名、教員数36名。1年生から個人所有iPad1人1台活用をおこなっている。1人1台活用は全国に先駆けて、2014年度から開始した。本校では「考えるを考える学習」であるミューズ学習という特設の授業を設定し、比較する」「つなげる」「分類する」「多面的に見る」「構造化する」「評価する」の6つのわざと、ベン図やボーン図などのシンキングツールを対応させて、一つずつ習得と活用を行っている。このような思考力育成の土台を大切にしながら、2021 年度に「STEAM 化」の実証を開始した。

お問い合わせ先
| 実証事例名 | STEAM化ごんぎつね普及計画 |
|---|---|
| 受託事業者名 | 学校法人 関西大学 初等部 |
| 実証パートナー名 | 京都府教育委員会、宮津市教育委員会、関西大学 |
| 実証年度 | |
| 事業カテゴリー種別 | |
| 実証地域 | 京都府、宮津市、吹田市、高槻市 |
| 実証校 | 関西大学初等部 |
| 対象 | |
| 対象学年 | 小3〜小6、大学初年次教育、教育委員会(公立学校教員) |
●このサービスをご覧の方はこんなサービスもご覧になられています。
-
プロスポーツチーム等との連携による「新し...
地域のスポーツ資源の力をフル活用し、市内の子どもたちが、各自の興味・関心・能力に合わせて安全・安心にやりたいスポーツを持続的にできる環...
-
自ら課題を発見・設定するPBLの開発とその実...
・中高生がゼロから課題を発見・設定するPBLの開発と提供 ・中高生がゼロから課題を発見・設定することを支援するための社会人向け研修の開発と...
-
企業・チーム等とのパートナーシップによる...
当社グループが沖縄県うるま市と連携して取組む、持続的可能なスポーツ環境の構築・スポーツビジネスの創出に向けたアプローチ手法が、環境の異...
-
学校内オルタナティブ教育に関する実証
不登校・不登校傾向にある生徒に、ICTを活用した「教室」以外の場(「和ルーム」や自宅)における、個別学習計画の作成や学びの場を提供する。そ...
-
温泉旅館街(リビングラボ)を学び場とした...
全国の温泉街における課題解決を題材としたイノベーション人材教育プログラム 全国にある温泉旅館街に、展開可能な人材教育プログラムとして、...
-
Edtechを利用した探究と教科学習の連動によ...
-
ルールメイカー育成プロジェクト2021
既存の校則やルールに対して生徒が主体となり、先生・保護者などの関係者との対話を重ね納得解をつくること(ルールメイキング)を通して、課題...
-
ふるさと納税を活用した教育資金獲得におけ...